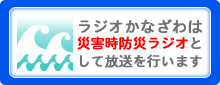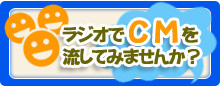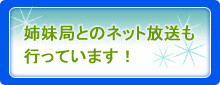©石川県観光連盟
名峰白山と峰続きの山々を背景に広がる町。大地がもたらす恩恵は内陸部に集落を形成し、中世は加賀における政治経済の中心地として、江戸時代には宿場町として栄えました。古(いにしえ)の史跡と街道沿いの町並みが先人の足跡を物語っています。長い年月の中で野々市市はどのように築かれたのでしょうか。歴史を振り返り、その歩みをたどってみましょう。解説にラジオ劇や講談を交えてお送りします。解説[東四柳史明]金沢学院大学名誉教授、講談[月亭方気]、演劇[大輔 柳原成寿 中元ミレイ]、ナレーション[綿谷尚子]。
【放送項目 前編】
舘残翁(たちざんおう)の郷土史研究
野々市市の歴史研究に尽力した郷土史家です。慶応三年(1867年)に野々市で誕生した舘残翁は、大乗寺や郷土の歴史発掘に生涯を捧げました。
収集した資料や、貴重な研究成果は後の郷土史研究の礎となりました。
富樫氏と馬図
馬図を描いた富樫氏は長谷川等伯の談話を記した「等伯画説」に登場します。話には雪舟が登場し、富樫氏の描いた馬図を「一段見事ニテ」と褒めています。能登畠山氏が馬図が欲しいと願い出た話や七尾地区との交流も伝えます。
大乗寺開山
富樫氏の外護や支援を受け野々市に開山した大乗寺の歴史を伝えます。
住職は教線の拡大を図り、やがて曹洞宗總持寺の開山につながりました。